中村桂子のつぶやき
ー緑に支えられている私たち人間ー
中村桂子のつぶやき―第十九回 2023.6.25
<KYOTO地球環境殿堂入りなさるジル・クレマンさんの素晴らしさ>
私も今回初めてこのお名前を知ったのですが、著書をいただいて拝読し、たくさんのことを教えられました。
フランスの庭園デザイナーですから恐らく始まりは「ヴェルサイユ宮殿の庭園」のようなものから入られたのではないでしょうか。けれども今は「庭師」と称されているのでわかるように自然を活かした庭を作っています。
最初に持ったのが「動いている庭」という概念です。多様性や進化を意識して庭を考えているうちに、倒木に意味が見えてきたり、モグラの大切さに気付いたりする過程がとても面白く、そのようにして生まれた庭の写真は魅力的です。
今では、「地球という庭」という概念を出しての庭づくりをしています。この時大事なのが、デザイナーでなく庭師であること。つまり外からの意識でなく、中に入り込んでの庭づくりになります。人間は、地球という庭の中で生きているというとらえ方は面白いと思います。中にいるという感覚は、私の「生命誌」と重なりますので、お話をするのを楽しみにしています。外からいじり回すのはもう止めましょうという仲間として。
今や、ヨーロッパとか日本とかの区別をする時ではありません。地球を意識して、その中でいかに楽しく生きるかということが大事と考える人が協力していく時だとクレマンさんの本を読んで思いました。
崖線は、まさにそんなことを考えさせてくれる場です。私はポチポチしか動けませんが、皆様の活動の大切さを改めて思った次第です。
付録: 「杜人」の矢野さんともう一人の土の達人高田さんが、我が家の庭の手入れをして下さいました。置いていかれたのが、土を柔らかくする棒なのです。別々にいらした二人が全く同じものを置いていったのが面白い。風と水の道を作っていただきましたので、見事に土が柔らかくなっているのですが、それが続くように日常棒で柔らかくしなさいということなのです。面白いのは、硬いところを無理してつつかないで柔らかいところをより柔らかくしなさいという指示です。人間の力で強引にというやり方をしないことという教えです。
中村桂子のつぶやきー第十八回 2023.5.24
<京都府綾部町でいろいろ勉強しました>
人口3万人の、いわゆる限界集落と呼ばれるところがたくさんある山間の町です。
それはすなわち水源にあるということですから、それを活かすというか、逆手に取るというか、「水源の里」として元気よく暮らしている魅力的な町なのです。
若い移住者が集落に溶け込んでいる様子、おばあさん3人組が美味しい栃もちを作って売り出しているところなど興味深いことはたくさんありましたが、今回書くのは「バラ園」です。
咲き誇っている様々なバラの一本一本にバラの名前と一緒に人が書かれた名札が小さく立っています。3000円出すと、苗一本と必要な肥料などが渡されます。それを植えて自分で面倒を見るのは大歓迎、でも忙しかったり遠かったりしてなかなか来られなくても大丈夫。ヴォランティアが世話をしてくれます。こうして見事なバラ園ができ、町の人はもちろん、外からも楽しみに来る方のある場になっているのです。
中央にあるのが「アンネ・フランクのバラ」、平和のシンボルとして大事にされています。
この町は、憲章の最初に「平和を願い祈りのある町にしよう」とあると知って、素晴しいと思いました。
自然の中にある人間として地に足をつけて生きたいと思っている一人として、とてもよい生き方をしている人たちの集まりだと感じたのです
みんなでつくるバラ園。私たちにもできることだなあと思ったのです。つながりを作る最も素敵な方法だなあと。
お考えお聞かせください。
中村桂子のつぶやき─第十七回 2023.1.18
<水と風(空気)の道をつくる─―確かに変わりました>
1月14日の土曜日、映画『杜人』の主人公である矢野智徳さんが、我が家の庭をみて下さいました。ここに暮らすようになって30年ほどになりますが、なにか自然の質が落ちているような気がして気になっていました。ハチやチョウやクモなどの小さな生きものたちが消えたり少なくなったりしていますし、植物たちもよく茂っているようでいながらどこか気になるという状態なのです。昨年対談の機会をいただいたこともあり、思い切ってお願いしました。
トラストの小さな森の活動を手伝って下さっている「グリーンワークス」の方たちが研修をしたいという希望もあり、20人近い人が朝9時半から夕方5時までの実習です。
私たちが持つのは鎌と移植ゴテ。風の道を作るには、木を揺らしてゆらゆら揺れる枝先を鎌で切り、風を通します。切る場所は風の揺れに合わせます。地面は移植ゴテを突き刺して水と風の道をつくります。土の上に置いた枕木が腐ってきているのを見て、ここはまったく風と水が通っていないから、悪い微生物たちが増えているので、ここに生えている樹も弱っている。よい土にするには道をつくらなければと……積んであるレンガを思い切りよく壊す……最初はびっくりしました。えっ、それってあり? もちろん、それはどうしてもはずさなければならないところだけです。次いで庭のあちこちに小さな穴を掘り、そこに炭と枝を入れることで、水と風の道を作る作業が続きました。
枝先を風の揺れに合わせて伐っておけば、その枝の様子に合った根が伸びていくのだそうです。土の上と下で呼応していることは分かっていても実際に手をかけて実感するのは、ただ頭で分かっているのとは違います。
作業が終わった時、確かに何かが変わっているのを感じました。具体的に説明するのは難しいのですが、これまでより土に眼が向くようになりましたし、小さなコテと鎌でちょっと手を加えることで自然は生き生きすると実感できます。今最も大事なのは土であるということは、最近強く感じていることですが、身近での体験で、体で分かった気分です。崖線に暮らす者として、大事なことを勉強しました。機会がありましたら見にいらして下さい。
実は、中川さんから神宮外苑問題について書いたらどうですかというメールをいただきました。本当に大事なことですが、ここまで問題点が明らかになっても平気で高層ビルを建てる方向に動く人々がいるということに絶望しかないという状態になってしまいました。それがよい選択だと思っているのか、とにかくお金が動くことをよしとしているのか。あまりよいことが書けませんのでしばらく考えたいと思っています。お考えお聞かせください。
中村桂子のつぶやき コメント欄
皆さまのお声をお待ちしています。下記よりお気軽にお寄せください。
-
#5
社 孝太郎 (火曜日, 15 8月 2023)
私は崖線の会員ではありませんが
今日久々に“つぶやき”を読ませて
頂きますと、第18回の綾部で
栃もちにも触れていましたので
自然と共に生きてきた日本人の食生活をまとめた良い本がありますのでご紹介させて頂きます。
“栃と餅・野本寛一・岩波”です。
いつもお忙しくされていますが
ご関心あれば、ご覧ください
-
#4
伊藤千加子 (月曜日, 05 12月 2022 15:33)
中村先生のつぶやき 第十一回
土のお話、是非、多くの人々に読んでもらいたいです。
今日は「世界土壌デー」ですね。
「国際土壌の10年」も残り少なくなってしまいましたね…。
土のこと、土を作ってくれている生き物のおかげで私たちが生きていられるということ、多くの人々に知ってほしいですね。
-
#3
岩井篤 (水曜日, 01 6月 2022 20:27)
戦後の焼け野原から脱却するために経済成長を追い求めて環境、健康、安全などを軽視してきた日本が、21世紀にはいって、成熟国家としてようやく舵を切り直していたはずなのに、依然として金儲けのために貴重なみどりや歴史に支えられた空間特質を破壊する開発計画が罷り通るのを見るのは悲しい限りです。現在は環境審議会で審議されているようですが、適正な判断が為されることを期待するのみです。
-
#2
松崎加寿子 (木曜日, 10 2月 2022 15:01)
そうなんです。2月10日の東京新聞朝刊 神宮外苑 再開発を承認 100年の森 900本近く伐採へ とります。このような野蛮な 歴史を無視 未来を無視した行為がまかり通るわけありません。
-
#1
岩井 篤 (木曜日, 10 2月 2022 14:47)
神宮外苑を永年見守り人々に癒しと安らぎを与えてきた樹木たちが伐採されてしまうのは樹木たちからみれば人間による酷い仕打ちでしょう。移植する、若木を植樹するからよいではないかというのは人間の勝手な言い分で、伐採され又は強制的に移転させられる樹木たちにとっては残酷な話です。人類は自然を征服するのではなく自然と共生するべきであることが漸く理解されつつあるこの時代に、企業の利益のためにこのような計画が罷り通ることは許されないと思います。現状を変えることなく神宮外苑の現在の空間的特質を継承することが重要と思います。
中村桂子のつぶやき 2021年、2022年はアーカイブに移動いたしました。
*2021年6月5日「崖線みどりの絆・せたがや」会長の中村桂子のコラムが始まりました。「緑に支えられている私たち人間」をテーマに、不定期に掲載いたします。どうぞお楽しみに。
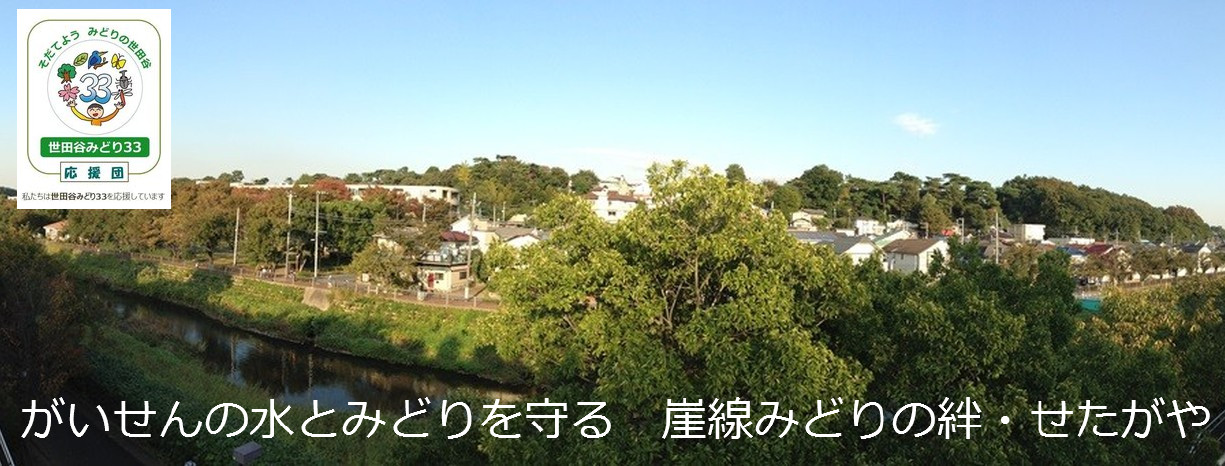
磯田 久美子 (水曜日, 06 3月 2024 15:08)
初めまして、中川さんの紹介で訪れました。崖線沿いのみつ池近くの小さな家を買って20年になります。ジル・クレマンさんの”The Garden in Movement”、予告編だけ拝見し、庭の規模は違えど共感できるものがありました。
ここに住み始めた頃、うちの小さな庭には神明の森の植生に近いヤブミョウガやカエデ、イヌシデ、南天が勝手に生えてきて難儀しました。
このままでは森の一部に還ってしまう!せっかく土地付きで買ったのに!!
抜いても抜いても生えてくるので、あきらめてカエデ3本、南天1本を残して庭木にしたら、それ以降新しい苗がわさわさ生えてくることがなくなりました。自然と折り合いがついたのでしょうか?
値段をつけて土地を売り買いしているのは人間だけで、崖線の長い歴史のいっとき、人は棲む場所を少しお借りしているだけなのかもしれませんね